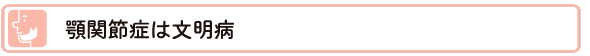
顎関節症とは
顎関節症という病名は、日本では顎関節の痛みと雑音、そして開口障害の症状を呈する慢性疾患の総称名です。この病気の発生率は、日本では13.6%、アメリカでは7%程度といわれています。しかし、学者によって発生率の値が異なり、2人に1人が予備軍であると言っている方もいます。私も統計を取ったことはありませんが、診療しながらの感触では、顎になんらかの症状を持っている方が非常に多いように思います。
顎関節症の症状
顎関節症とは、どんな症状が現れるかをお話します。
この病気の症状は、開閉口時に顎にパキッという音がする、口が開きにくい、というような軽症のものから、口が開かなくなったり、極めて激しい頭痛で日常生活に支障をきたすような重症まであります。また耳鳴りや肩こりなどの症状がでることもあります。最もびっくりするのは、ある日突然、口が1cm程度しか開かなくなり、それより痛くて開けられなくなることがあります。
しかし、そのような状態が起こる前に、予兆といえる症状があります。それは、開閉口時に顎に軽い痛みを感じガクガク音がする、朝起きると顎がこわばって動きにくい、といような症状です。これを放置していると、突然口が開かなくなることがあるのです。
頭痛や肩こりの激しい患者さんでは、まず脳神経科、眼科や耳鼻科などを受診されると思います。そこではMRIやCTを撮って検査されますが、顎関節症であれば結果は異常なしと診断されるのです。
顎関節症は文明病?
顎関節症は、どうして発生するのでしょうか。
それを説明する前に、顎関節が年齢と共にどう変化するかをお話しします。大西先生が、アフリカのナイジェリアの田舎に住むヨルバ族という原住民を調査されました。その報告では、歳をとるにしたがって歯の噛む面は磨り減り平らになっていきます。それにともなって顎関節の下顎頭(大腿骨では大腿骨頭に相当)は変形し、その度合は歯のすり減りが大きくなると変形度も大きくなるそうです。しかし、顎関節症の患者さんはほとんどいなかったというのです。もちろん原住民には、歯科治療は全く行われていません。その生活様式は古代の人々に通じます。
そこで、この調査結果から言えることは、古代の人々には顎関節症という病気はほとんど無かったと推測されるのです。顎関節症が文献にみられるのが1822年(文政4年)頃からですが、真に研究が始まるのは第二次世界大戦後からです。したがって顎関節症は、古代の人々にもあったのでしょうが、今日ほど多くの方が発病していたとは考えにくいのです。
顎関節症は、日本や欧米のように文明が発達し、歯科治療の行き届いた国の人々に多くみられる、いわば文明病なのです。
顎関節症の原因と治療
顎関節症の原因について、テレビなどで「くいしばり」や「頬杖」などの悪習慣、さらには「ストレス」などと言っている研究者がいます。しかし、これらは顎関節症の真の原因ではありません。なぜなら、くいしばりや頬杖の力は、奥歯で支えられていて決して顎関節に負担としてかかることはないからです。またストレスによる発病には、医学的根拠は全くありません。
顎関節症の原因は、今日の歯科学では解明されていないのです。
私が、顎関節症の患者さんの咬み合わせの治療をすると、顎関節症は完全に直るのです。そして治療には、薬は全く必要ないのです。したがって、顎関節症の原因は咬み合わせの狂いから起こると考えています。
顎関節症はどのように治療するのでしょうか。
まず、スプリントというマウスピースのような装置を用いて痛みをとります。痛みが取れたら、次に行うのが咬み合わせの治療です。そして最後に、二度と顎関節症で苦しむことがないように永久的な治療を行います。スプリントと咬み合わせ治療の組み合わせが、顎関節症の最も新しい治療法です。

